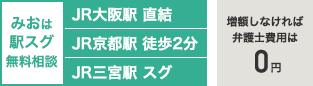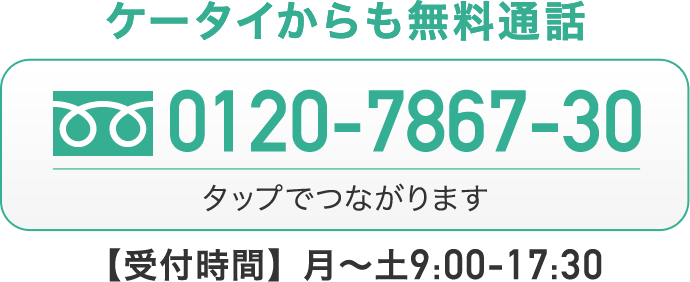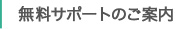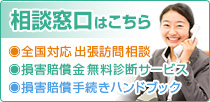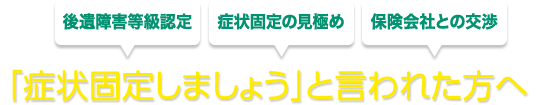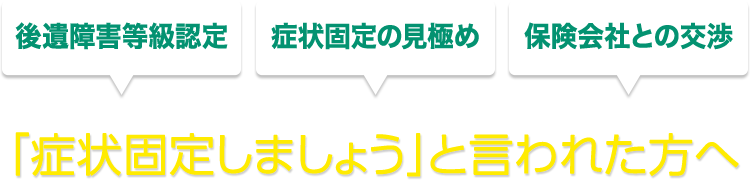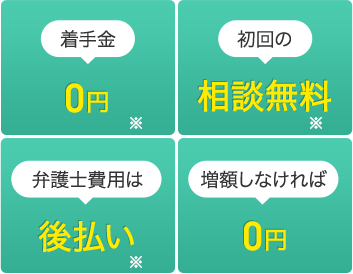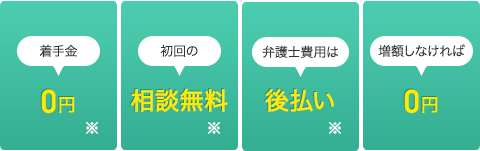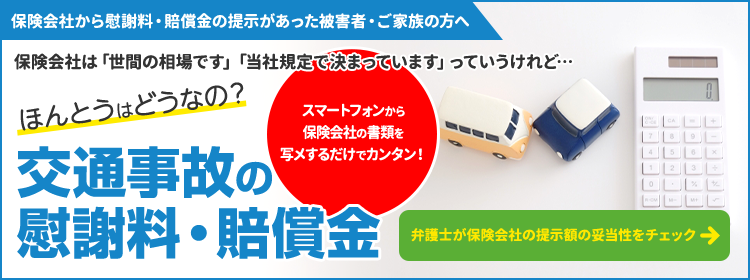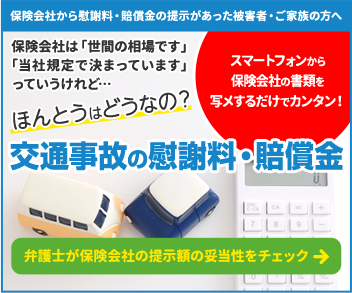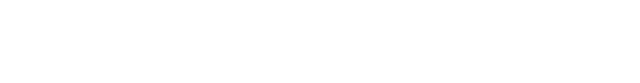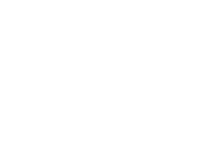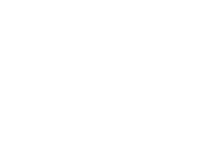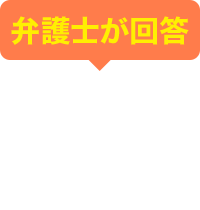交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。
後遺障害等級が上がった事例
弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。
事例15
- 受任前
- 併合8級
- 解決
- 併合7級
- 症状・部位
- 脊柱変形、足指用廃
- 後遺障害保険金
- 相談前
- 819万円
- 相談後
- 1,051万円
※自賠責保険金
相談のきっかけ

被害者のOさんは、交通事故により第12胸椎の圧迫骨折等の怪我を負い、脊柱の変形、1足の足指の全部の用廃という後遺障害が残りました。後遺障害等級については、脊柱の変形で12級、1足の足指の全部の用廃で9級等により、併合8級の認定を受けました。
Oさんは、脊柱の運動障害や股関節の可動域制限について、後遺障害の認定を受けることができなかったことに不満があったため、当事務所にご相談に来られました。
解決までのステップ
弁護士は画像をもとに可動域制限の因果関係を主張し、後遺障害等級を上昇させました。

Oさんが訴えていた脊柱の運動障害については、「水腫はいずれ吸収されるため、軟部組織の変性まで認められない」という理由で、残念ながら異議申立ては認められませんでした。一方の股関節の可動域制限については、画像を撮り直すなどして可動域制限が生じた因果関係を主張することで、後遺障害等級12級の認定を受けることができました。
股関節の可動域制限が新たに認められたことで、当初の併合8級から併合7級へと等級を上昇させることができました。
この事例のまとめ
自賠責の後遺障害保険金は、8級で819万円、7級で1,051万円となり、200万円以上もの差が出てきます。また、労働能力喪失率も8級では45%、7級で56%となっています。今回は画像が決め手となった事案でした。
他の事例を見る
- 10級
- 8級

弁護士の指示による追加検査の結果、新たな障害が判明。10級から8級へ。
- 7級
- 併合4級

追加検査の実施、事故前後の生活状況の変化を指摘し、適正な等級を取得。
- 9級
- 7級

後遺障害の内容を検討し、2度目の異議申立てで適正な等級を取得した事例。
- 2級
- 1級

ご家族の介護の大変さを証拠化して異議申立てを行い、2級から1級へ。
- 5級
- 併合4級

小さな後遺障害を見落とさずに異議申立てを行い、適正な等級認定を取得。
- 14級
- 10級

弁護士の指示による追加検査の結果、新たな障害が判明。14級から10級へ。
- 14級
- 7級

診断書の内容について医師に追加検査と意見書の作成を依頼。14級から7級へ。
- 3級
- 2級

後遺障害による支障についての詳細な調査結果を受け、3級が2級に上昇。
- 14級
- 12級

弁護士の検査精査により、事前認定での「骨片の見逃し」が発覚した事例。
- 12級
- 7級4号

聞き取りや診断書の内容から詳細な立証資料を作成し、12級から7級に上昇。
- 12級
- 9級

専門的知識にもとづく適切な判断と対応により、12級が9級に上昇した事例。
- 12級
- 9級

医学知識にもとづいた正確な見立てにより、適正な等級が認定された事例。
- 9級
- 7級

弁護士が必要な資料を取り揃えたことで、9級から7級に上昇した事例。
- 非該当
- 14級

被害者が訴える症状から等級認定の可能性を見出し、適切な対応で14級を取得。
- 併合8級
- 併合7級

画像の撮り直しを行い可動域制限を主張した結果、併合8級から併合7級へ。
- 14級
- 12級

手術内容に関する意見書をもとに異議申立てを行い、12級の認定を得た事例。
- 非該当
- 14級

被害者への聞き取り調査と医師との面談を活かして、非該当から14級の認定へ。
- 12級
- 併合11級

等級変更の可能性があり、資料取付、異議申立を行った結果、12級から11級へ。
- 14級
- 12級

医師の協力を得て画像の精査と異議申立を行った結果、14級から12級に上昇。
- 併合3級
- 併合1級

詳細な日常生活状況報告をもとに異議申立を行い、併合3級から併合1級へ。
- 14級
- 12級

主治医の意見書等を取得し、後遺障害等級が14級から12級に変更された事例。
- 非該当
- 12級13号

認定された後遺障害等級の妥当性を判断し、異議申立を行うことで等級が上がった事例。